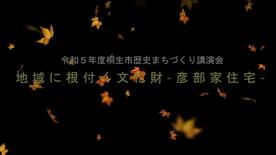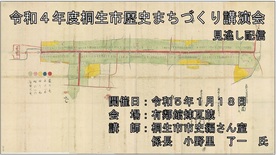歴史まちづくり動画の配信
令和6年度に開催した桐生市歴史まちづくり講演会の様子を市公式YouTube「桐生市チャンネル」に配信しました。是非ご覧ください。
平成30年1月に「桐生市歴史的風致維持向上計画」が国の認定を受けました。
このことを多くの市民の皆さまに知っていただくとともに、歴史まちづくりの推進啓発等を図るため、歴史的風致に関連した動画をユーチューブ「桐生市チャンネル」により配信します。ぜひご覧ください。
動画配信
令和6年度歴史まちづくり講演会見逃し配信
令和6年11月29日に開催した桐生市歴史まちづくり講演会の様子を配信しました。
“織都桐生”案内人の会の八染 和弘さんに「重伝建地区の街並み今昔-明治37年の地図と現在-」と題して講演いただきました。是非、ご覧ください。
(上の画像をクリックするとユーチューブ「桐生市チャンネル」に移動し、動画の再生が始まります。)
講演会のテーマ「重伝建地区の街並み今昔-明治37年の地図と現在-」
- 重伝建地区の現在の街並み
- 明治37年の地図と現在の街並みを照らし合わせ考察
- 現在の街並みの昔の姿をたどる
動画配信
令和5年度第2回桐生市歴史まちづくり講演会見逃し配信
令和5年11月22日に開催した桐生市歴史まちづくり講演会の様子を配信しました。
重要文化財彦部家屋敷当主の彦部 篤夫さんに「地域に根付く文化財-彦部家住宅-」と題して講演いただきました。是非、ご覧ください。
(上の画像をクリックするとユーチューブ「桐生市チャンネル」に移動し、動画の再生が始まります。)
講演会のテーマ「地域に根付く文化財-彦部家住宅-」
- 文化財の位置づけと桐生市内の文化財について
- 彦部家屋敷の歴史
- 彦部家の四季と文化活動紹介
動画配信
令和5年度第1回桐生市歴史まちづくり講演会見逃し配信
令和5年6月20日に開催した桐生市歴史まちづくり講演会の様子を配信しました。
郷土史家の奈良 彰一さんを講師に招き、桐生祇園祭の屋台と鉾の見どころについて講演いただきました。是非、ご覧ください。
(上の画像をクリックするとユーチューブ「桐生市チャンネル」に移動し、動画の再生が始まります。)
講演会テーマ「桐生祇園祭 屋台と鉾の見どころ」
- 桐生祇園屋台について
- 今年(令和5年度)の祇園祭の見どころ
- 今年(令和5年度)の年番町の屋台紹介
動画配信
令和4年度第2回桐生市歴史まちづくり講演会見逃し配信
令和5年1月18日に開催した桐生市歴史まちづくり講演会の様子を配信しました。
桐生市市史編さん室の小野里係長を講師に招き、桐生の町立てについて講演いただきました。是非、ご覧ください。
(上の画像をクリックするとユーチューブ「桐生市チャンネル」に移動し、動画の再生が始まります。)
講演会のテーマ「桐生の町立てについて」
- 桐生新町(現在の本町1~6丁目、横山町及びその周辺)は、豊臣氏の小田原征伐後、関東に入国した徳川家康によって創り出された。
- 桐生新町は当時田畑もなく、今後開墾したとしても可耕地が増える見込みがない土地であった。
- 町立てにあたっては、現在の東京都八王子市がモデルとなっている。
動画配信
令和4年度第1回桐生市歴史まちづくり講演会見逃し配信
令和4年10月23日に開催した桐生市歴史まちづくり講演会の様子を配信しました。
一般社団法人桐生倶楽部の村田理事を講師に招き、桐生倶楽部と桐生倶楽部会館の歴史等について講演いただきました。是非、ご覧ください。
(上の画像をクリックするとユーチューブ「桐生市チャンネル」に移動し、動画の再生が始まります。)
講演会のテーマ「桐生倶楽部と桐生倶楽部会館について~まちとともに103歳の現役会館~」
- 桐生倶楽部会館は、大正8年に建てられた、国内初期のものとされているスパニッシュコロニアル意匠が見られる建物で、現在も当時の姿が良好に保たれている。
- 名士の社交場として利用され、多くの著名人をもてなしてきた。
- 現在は、建物を一般公開する等、時代に合わせて活用形態を変化させている。
桐生市歴史まちづくり動画~地名から学ぶ、桐生町から桐生市の変遷~
桐生市は、大正10年に全国で84番目の市として誕生しました。
今回、市制施行100周年を記念し、桐生市の歴史的風致を構成する背景となっている市域の変遷や歴史、地名の由来などを紹介する動画を制作しましたので、是非ご覧ください。
(上の画像をクリックするとユーチューブ「桐生市チャンネル」に移動し、動画の再生が始まります。)
桐生町から桐生市の変遷について
- 現在の桐生市とその周辺は、近世にかけて、桐生領54か村と言われ、小さな54の村々が存在し、1つの経済的なまとまりがあったとされている。
- 桐生領54か村の村々が分村、合併を繰り返し、明治22年に桐生市の前身である桐生町が誕生する。
- 市制施行後の桐生市は、近隣の村との合併を繰り返しながら面積を拡大し、現在に至る。
桐生市歴史まちづくり動画~桐生ゑびす講について~
桐生ゑびす講は、桐生西宮神社で毎年11月19日、20日に開催されている、桐生市を代表する歴史的風致です。
また、桐生ゑびす講は、明治34年に桐生西宮神社が兵庫県にある西宮神社本社の直系分社として分霊勧請されて以来100年以上続いており、毎年多くの方が参拝に訪れています。
今回、桐生ゑびす講について桐生西宮神社総務の岡部信一郎さんにご講演をいただく動画を制作しましたので、是非ご覧ください。
(上の画像をクリックするとユーチューブ「桐生市チャンネル」に移動し、動画の再生が始まります。)
桐生ゑびす講について
- 桐生ゑびす講は、明治34年から100年以上続いている。
- 桐生では、古くからゑびす信仰が盛んであった。
- 桐生西宮神社は、関東で唯一西宮神社本社の直系分社として分霊勧請されているため、関東一社と言われている。
桐生の今昔 古写真から見る桐生が岡公園
桐生が岡公園は、明治28年に小島春比古(当時桐生町長)が土地を寄附したことをきっかけに、町民らが私財を投じながら段階的に整備され、現在に至ります。動画では、主に桐生が岡動物園下の通称女神像広場、藤棚広場、そして山手通り周辺を取り上げています。今も残る当時の歴史的資源を紹介すると共に、古写真と現在とを比較しながらこれらの歴史を紹介します。歴史に思いを馳せながらぜひ散策してみてください。
(上の画像をクリックするとユーチューブ「桐生市チャンネル」に移動し、動画の再生が始まります。)
桐生が岡公園について
- 桐生が岡公園は明治28年に当時の桐生町長である小島春比古が、所有する敷地を寄附したことがきっかけで整備が始まった。
- 一大公園化を目指した先人たちの思いが詰まっており、桜や眺望を楽しむ人々の憩いの場所であった。
- 歴史資源として、玉石積みの石垣、石階段、腰掛石、歩道高欄、水路など、様々なものが残されている。
桐生祇園祭の歴史と魅力
桐生市の代表的な歴史的風致である桐生祇園祭ですが、令和2年は新型コロナ感染症の影響で神事のみ実施され、その他の行事は中止となってしまいました。翌年の開催を願いつつ、次回開催の祇園祭をより楽しめるよう今回「桐生祇園祭の歴史と魅力」について祇園祭礼研究家の奈良彰一さんに紹介していただく動画を制作しましたのでご覧ください。
(上の画像をクリックするとユーチューブ「桐生市チャンネル」に移動し、動画の再生が始まります。)
桐生祇園祭について
明暦2年(1656年)の記録が残る360年以上続く桐生を代表する伝統的な祭礼。現在は毎年8月の桐生八木節まつりと同日に挙行されているが、本来は別の祭礼である。惣六町(本町1~6丁目)と横山町の7町会により行われ、毎年、惣六町から天王番(天王町)を持ち回る。令和2年(2020年)は本町5丁目が天王番であった。
動画のポイント
- 桐生祇園祭は、美和神社(宮本町二丁目)に合祀された八坂神社(明治4年まで本町3丁目にあった)の祭典
- 明暦年間に子供の手踊りから始まり、疫病退散を目的としていた
- 大まかな行程としては、挨拶廻り、前日の出御の儀、初日の衣装付け届け、本祭(2日目)の神輿渡御、3日目の神輿還御、千秋楽付け届けなどがある
- 出御では、御神輿に神様を移し、天王町に設置された御旅所まで運び安置する
- 神輿渡御は、天王町からスタートし、全7町会を練り歩く重要な行事である
- 桐生には各町会に1台ずつの6台の巨大な屋台、3丁目と4丁目に1基ずつの2基の鉾、3対の大幟が現存
- 令和3年は、本町6丁目が天王番となる
歴史的風致とは
地域におけるその固有の歴史および伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物およびその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境のことで、ハードとしての建造物とソフトとしての人々の活動を合わせた概念です。
桐生市における代表的な歴史的風致として、桐生新町伝建地区周辺(ハード)で行われる桐生祇園祭(ソフト)が典型的なものと言えます。
関連情報
- 桐生市歴史的風致維持向上計画
- 過去の歴史まちづくり講演会
- 「歴史まちづくりカード(歴まちカード)」の配布
- 歴史的風致形成建造物の動画配信
- 歴史まちづくりワークショップ
- 桐生祇園祭保存会(外部リンク)

- ユーチューブ「桐生市チャンネル」(外部リンク)

ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 歴まち・街路係(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3792
ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
都市整備部 都市計画課(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:都市計画係 0277-32-3784
歴まち・街路係 0277-32-3792
景観係 0277-32-3787
用地係 0277-32-3799
ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。