国保税の決め方
国保に加入されている皆さんが、病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた国保税と国の補助金などでまかなわれています。国保税は、国保の運営を支える重要な財源です。この制度を維持していくため、国保税の納期内納付をお願いします。
40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の被保険者については、医療分と後期高齢者支援金分の他に介護分を国保税として納めていただきます。
国保税の決め方
国保税は、その年に予測される全医療費から、国などの補助金や皆さんが病院などに支払う一部負担金を差し引いた金額を、国保税として皆さんに負担していただいているものです。これを、所得割額、均等割額、平等割額の組合わせで計算して、一世帯の国保税額が決まります。後期高齢者支援金分や40歳以上65歳未満の人の介護分も同様に決められます。
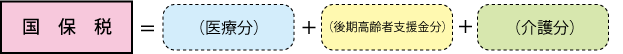
所得割額:加入者の前年の所得(基礎控除額の43万円を引いた額)に応じて課税
均等割額:加入者数に応じて課税
平等割額:一世帯いくらと課税
令和7年度 国保税率の改定について
高齢化や医療の高度化等により保険給付費が増えるなか、国民健康保険財政の安定化のため、以下のとおり、令和7年度の国保税率を改定しました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
背景
令和7年1月に群馬県が示した、桐生市が県に納める令和7年度国保事業費納付金総額は約28億8千万円で、現行の国保税率を据え置いた場合には、令和7年度国保特別会計予算ベースで約6億1千万円の不足が生じ、税収によっては令和7年度内にも基金が枯渇する状況となりました。
本市の国保の現行税率は、平成30年度の国保都道府県化以降、被保険者の負担軽減のため、保有する基金を活用し、標準保険料率より低い水準に据え置いてきましたが、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の全ての項目において、市町村ごとの保険料率の標準的な水準である市町村標準保険料率との乖離が大きいことから、保有する基金の活用額を抑制し、当面の間、可能な限り標準保険料率より低い税率の設定を可能なものとするため、現行税率の見直しを行いました。
所得割率の引上げ
|
区分 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
| 基礎課税額(医療分) |
5.8% |
6.8% |
| 後期高齢者支援金等課税額 |
2.2% |
2.6% |
| 介護納付金課税額 |
1.9% |
2.2% |
被保険者均等割額の増額
|
区分 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
| 基礎課税額(医療分) |
21,000円 |
25,800円 |
| 後期高齢者支援金等課税額 |
7,600円 |
10,300円 |
| 介護納付金課税額 |
9,000円 |
10,900円 |
被保険者平等割額の増額
|
区分 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
| 基礎課税額(医療分) |
15,000円 |
19,600円 |
| 後期高齢者支援金等課税額 |
6,600円 |
7,600円 |
| 介護納付金課税額 |
4,900円 |
5,600円 |
国保税の計算方法
医療分(国保に加入するすべての人) (令和7年度)
所得割額:(前年分の総所得金額等-基礎控除額430,000円)×6.8%
均等割額:被保険者数×25,800円
平等割額:1世帯あたり19,600円
注:上記の合計額が医療分の年税額です。最高限度は66万円です。
後期高齢者支援金分(国保に加入するすべての人) (令和7年度)
所得割額:(前年分の総所得金額等-基礎控除額430,000円)×2.6%
均等割額:被保険者数×10,300円
平等割額:1世帯あたり7,600円
注:上記の合計額が後期高齢者支援金分の年税額です。最高限度は26万円です。
介護分(40歳以上65歳未満の人) (令和7年度)
所得割額:(前年分の総所得金額等-基礎控除額430,000円)×2.2%
均等割額:被保険者数×10,900円
平等割額:1世帯あたり5,600円
注:上記の合計額が介護分の年税額です。最高限度は17万円です。
令和7年度 モデルケース
税額の試算
エクセルによる国保税の試算ができます。下記からダウンロードしてください。
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療保険課 保険税係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8266
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
