ふくさ包み【ふろしきの包み方】

ふくさ(袱紗)とは、やわらかくふっくらしたという形容詞から生まれたといわれています。
やまと言葉であることもあって、服紗、帛紗、覆紗、和巾、富久紗など、いろいろな漢字が当てられています。
贈答儀礼にふくさが使われるようになったのは平安中期。贈答品にかけて、ほこりをよけて持参する風習が、公家社会ではじまりました。
定着するのは室町のころ。江戸中期になると生活全般が奢侈(しゃし)になって、ふくさも禁止令の対象とされたようです。
このようなことから現在も東京を中心とした東日本では、ふくさの使用が少ないといわれます。
包みふくさは絹の袷(あわせ)が多く、先染めの織りが後染めのものより格が上、本つづれ織りを最上とします。
包み方
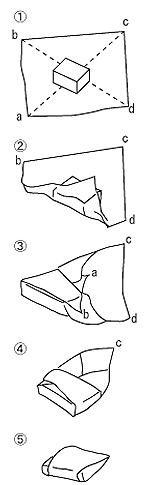
結び目がないので、形に添ってしっかり包み込みます。弔事以外で先様に差し出すときは、右開きになるようにします。
- 箱は中央におく。
- 左手側のaをかける。
- b側の角を包む。
- dも包む。
- cをかぶせる。弔事は合わせが逆になる。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 生涯学習課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:社会教育係 0277-46-6465
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










